「親が認知症になってしまった場合、親の預金口座が凍結されてしまう」-こんな話を聞いたことはありませんか?もし親が認知症になってしまった場合、たとえ家族であっても親の預金口座からお金を引き出せなくなる可能性があります。それでは、私たちはどのように備えればよいのでしょうか?
この記事では、認知症による預金口座凍結のリスクと、その対応策についてわかりやすく解説していきます。
認知症になった親の預金口座はどうなるか?
親が認知症になった場合、親の銀行口座はどうなってしまうのでしょうか。親が認知症になった場合、施設入居費、医療費、生活費など多額の出費があるかもしれません。親のために支出する場合であっても、家族は親の預金を払い出すことはできないのでしょうか?
親が認知症になった場合、家族であっても親の銀行口座から預金を引き出せなくなる可能性は高いです。
令和2年8月5日に金融庁から公表された報告書においても、以下の問題点が指摘されています。
- 高齢顧客については、認知判断能力の低下により、従前のような金融取引が困難になる場合や、身体機能の低下等により、金融機関の窓口に本人が赴けなくなる場合がある。このような場合、その家族や公的機関が本人に代わって金融機関の窓口に預金の引き出し等に行く必要があるが、本人意思が確認できないことなどを理由として、こうした手続が認められないといった事例が多く指摘されている。
- 認知判断能力が低下した場合、本人意思が明確に確認できないという同様の理由から、本人であっても預金の引き出し等が認められないことも指摘されている。
- 本人の委任状を持参した場合でも、その信憑性が確認できないとして、代理が認められないことがある。
出所:令和2年8月5日 金融庁 金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書
それでは、銀行側は預金者が認知症になった場合の対応をどのように考えているのでしょうか。まず、日本国内にある民間銀行のほとんどが加盟している全国銀行協会のスタンスをみてみましょう。
2021年2月18日に一般社団法人全国銀行協会から公表された「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会 福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」では、以下の考え方が示されています。
- 銀行においては、認知判断能力が低下した顧客との取引をする場合、民法上の法定後見制度である補助人、保佐人の同意を確認のうえ本人との取引を行う、あるいは成年後見人や任意後見制度にもとづく任意後見人を介して、代理取引を行うのが一般的である。
- 親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない(できない)場合において行う、極めて限定的な対応である。成年後見制度の利用を求めることが基本であり、成年後見人等 が指定された後は、成年後見人等以外の親族等からの払出し(振込)依頼には応じず、成年後見人等からの払出し(振込)依頼を求めることが基本である。
出所:2021年2月18日 一般社団法人全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会 福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」
全国銀行協会の基本的なスタンスは、親が認知症になった場合、親の銀行口座から預金の引き下ろしなどを行うためには、成年後見制度を利用しましょう、というものになっています。成年後見制度については、後ほど説明しますが、普通の人が利用するには結構ハードルが高い制度であり、利用もあまり行われていないのが現状です。
そのため、全国銀行協会も(一応)以下のような考え方も示してはいます。
認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の 医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる。
そのうえで、成年後見制度を利用していない前提で、認知症となった預金者の家族が預金の払い出しを求めた場合に対応するかどうかについての考え方を2022年5月16日に公表しています。
「不測の事態における預金の払出しに関する考え方について」
しかし、こちらを読んでみても、実際に家族が親の代理人として親の銀行口座から預金を引き下ろすことができるのかどうかは不明確であり、仮にできたとしても、払い出しができる金額や回数、資金の用途に制約があり、具体的な手続きも不明確です。
さらに、全国銀行協会は、「本考え方は、会員各行の参考となるよう取りまとめたものであり、会員各行に一律の対応を求めるものではなく、個別の状況等により、本考え方と異なる対応が取られるケースもあり得ることにご留意ください。」と述べており、それぞれの金融機関が、どこまで対応してくれるのかはわかりません。
それでは、個別の金融機関のスタンスについて、ホームページなどで公表されている内容をみてみましょう。
まずは、最大手の銀行(メガバンク)からみてみます。
三井住友銀行の場合
三井住友銀行のホームページには、「認知症の親の口座が凍結されたら預金引き出しできる?介護のための事前対策!?」という記事が掲載されています。
ファイナンシャル・プランナーさんが執筆した記事ですが、銀行の公式ホームページに掲載されているため、三井住友銀行の考え方に沿った内容と考えて良いでしょう。こちらの記事から大事なポイントを引用します。
- 預金は、預金者本人(口座名義人)が管理するのが原則です。本人以外の家族などが預金を引き出す場合には、本人の意思確認が必要です。「代理人指名手続」を行っていない場合は、本人と一緒に銀行の窓口へ出向き、手続きを行う必要がありますが、本人の様子から、認知症で判断能力に欠けると銀行が判断すると、口座からお金を引き出せなくなる場合もあります。預金の引き出しや解約などができなくなってしまうわけです。これは、詐欺や横領といった犯罪や口座の不正使用はもちろん、家族による使い込みなどを防ぐための措置になります。
- 全国銀行協会では、2020年3月末に「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料」(リーフレット)を発行しました。「認知症で生活費や医療費、介護費が引き出せないときには、まず取引銀行の窓口で相談をしてください」と記載されています。預金者本人の意思で引き出すのが原則ですが、本人が意思を明確に示せない場合でも、戸籍抄本などで家族関係が証明され、介護施設や医療機関の請求書などで使いみちが確認できれば、口座からお金を引き出すことができる場合があります。
以前は銀行ごとに判断が異なっていましたが、「まず銀行窓口へ相談を」という表現で、引き出せる「可能性」を明確に打ち出しています。ただし、リーフレットには、「継続的に預金の引き出しを希望する場合は、成年後見制度の利用を」ともあります。緊急時では対応してもらえる可能性がありますが、その後はきちんと体制を整える必要がありそうです。どのような対応になるかは、銀行で相談をしましょう。「認知症になって意思能力が失われる=口座からお金を引き出せなくなる」ではなく、書類などが整っていれば、法定後見人が決まる前であっても預金を引き出すことが可能なケースがあります。こうした情報を知っておくと、家族にとっても大きな安心につながります。
- 普通預金については、あらかじめ「代理人指名手続」を行っておく、または「代理人キャッシュカード」を作成しておくことで、指定された家族が代理人として引き出すことができます。
「代理人キャッシュカード」では、1回でATMでの1日あたりの限度額まで引き出しが可能ですが、「代理人指名手続」なら窓口での手続きでATMの引き出し限度額を超える金額も引き出せます。どちらも預金者本人に判断能力がある間に、銀行の窓口で手続きをしておきます。70歳を過ぎた親のことが心配になってきたら、話し合って手続きをしておいてもらうと良いでしょう。介護施設への入所などでまとまったお金が必要になり、定期預金の解約などを行う場合も、「代理人指名手続」を行っていれば代理人が行えます。
出所:三井住友銀行のホームページ「認知症の親の口座が凍結されたら預金引き出しできる?介護のための事前対策!?」https://www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/money-jiten/0042
上記の内容は、基本的には全国銀行協会から公表された考え方と同じといえるでしょう。つまり、親が認知症になった場合、家族が親の預金口座から引き出しを行うことはできず、成年後見制度の利用が必要になります。成年後見制度の利用ができない場合、銀行窓口に相談すれば預金を引き出せる可能性もありますが、あくまでそういう場合もありますというだけで、実際に預金を引き出せるかどうかはわかりません。
一方で、成年後見制度を利用しなくとも、親が認知症になる前であれば、あらかじめ「代理人指名手続」を行っておく、または「代理人キャッシュカード」を作成しておくことで家族でも普通預金の口座から預金を引き出すことができると明記されています。
三井住友銀行の「代理人指名手続」と「代理人キャッシュカード」については、こちらで内容をみることができます。
他のメガバンクの場合
他のメガバンクについて、三菱UFJ銀行とみずほ銀行のホームページには、預金者が認知症になった場合の銀行窓口の対応について説明した記事をみつけることはできませんでしたが、三井住友銀行の代理人指名手続きと同じようなサービスがありました。
三菱UFJファイナンシャルグループの「予約型代理人」サービス
https://www.bk.mufg.jp/news/news2021/pdf/news0308.pdf
みずほ銀行の代理人予約サービス
メガバンク以外の金融機関の場合
つぎに、メガバンク以外の金融機関についてはどうでしょうか。
筆者が横浜銀行、ちば銀行、福岡銀行のホームページをみたところ、認知症になった場合の対応としては成年後見制度の利用を促すにとどまり、メガバンクが提供する代理人サービスの提供もありませんでした。(2025年4月14日現在)
(参考)成年後見制度について
ここで、預金者が認知症になった場合の対応として金融機関が利用を促す成年後見制度について簡単に説明します。
成年後見制度は難しいのでここでは簡単な説明にとどめて、詳細については別の記事で解説します。
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるため法律行為における意思決定が困難な方々について、本人の 権利を守るために選任された援助者(成年後見人等)により、本人を法律的に支援する制度のことで、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によ って選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度のことです。
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる者や将来その者に委任する事務(本人の生活、 療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、 本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本 人に代わって行う制度のことです。
令和4年12月末日において、成年後見制度の利用者数は約24万人です。
出所:厚生労働省「成年後見制度の現状」令和6年4月 https://www.mhlw.go.jp/content/001102138.pdf
65歳以上の認知症の推計人数が令和4年時点において443万人であることから、認知症の人の数と比べても成年後見制度の利用は十分に行われていないといえます。
認知症の人数が増加しているにもかかわらず成年後見制度の利用が十分行われていないのは、制度が複雑で一般に知られていないことのほかに、つぎのようなデメリットがあるからと考えられます。
- 制度を利用するための手続が複雑であるため一般の人にはハードルが高く、申立てのための手数料や専門家(弁護士や司法書士)への報酬が発生する
- 制度利用後に成年後見人等への報酬を継続して支払う必要があり、金銭面の負担が大きい
- 親族以外の第三者(弁護士、司法書士等)が成年後見人等に選任されるケースが多く、これらの成年後見人等が財産管理を行う場合、認知症になった人の預金等の資産を本人や家族の希望どおりに利用できなくなる
- いったん成年後見制度の利用を開始すると、簡単にやめることができず、上記のデメリットが長期間続いてしまう
- 任意後見制度の場合、本人と任意後見人との間の契約により,任意後見人や任意後見人に委任する事務の内容について本人や家族の希望を反映させることができるが、本人が認知症になった後は任意後見制度を利用することはできない。
実際に親が認知症になった場合、何も対応していなかったらどうなるの?
ここで、親が認知症になった場合、事前に何の対策もしていなかった場合にどうなってしまうかについてまとめておきます。
- 親が認知症になり、認知判断能力を喪失した場合、親本人は自ら預金の引出しや金融商品の売却の意思表示を行うことができなくなることから、本人の預金口座や証 券口座は金融機関等により凍結される。
- 全国銀行協会は、本人の利益に適合することが明らかである場合(認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為など)に限り、依頼に応じることが考えられる、という考え方を公表しているが、個別の金融機関がどこまでどのように対応するかは不明確・不確実でありリスク高いと言わざるをえない。
- 親が認知症になった後では、金融機関の代理人サービスの利用、親子間の財産管理契約の締結、民事信託の設定、任意後見制度を利用することはできなくなる。親の預金口座から引き下ろしをするために何らかの制度を利用しようとすれば、法定後見制度の一択になってしまう。
- 法定後見制度を利用する場合、家族以外の第三者が成年後見人等に選任されて財産管理を行う(本人や家族が自由に本人の預金を使用できない)、成年後見人等への報酬を払わなければならない、法定後見制度の利用を自由にやめることができない、などのデメリットが以後継続することになる
対応策 認知症になる前にとりあえずやるべきことは?
事前に何の対策もしていなかった場合、大変なことになりそうですね。それでは、何から手をつければよいのでしょうか?
1.親とのコミュニケーション
いきなり実家に行って、親に銀行の代理サービスを申し込んでくれ、とか、任意後見契約を締結してくれ、といっても親から警戒されてしまい話をこじらせてしまうかもしれません。特に、普段親とのコミュニケーションが希薄になっているような人は要注意ですね。
はじめの一歩として、以下の内容を親に話してみてはいかがでしょうか。
- 認知症はだれがいつなってもおかしくない病気であること
- 親が認知症になった場合、銀行口座が凍結されてしまい、施設入居費、医療費、生活費など多額の出費がある場合に、それらの出費を家族が負担しなければならないかもしれないこと
- 親が認知症になった場合、家族の負担が大きくなる可能性があり、不安に感じていること
- 親が実際に認知症になった後では、認知症の対応策の選択肢が限られてしまうため、認知症になる前から準備を始める必要があること
- 早めに認知症の対応策を準備することにより、親自身の希望を認知症対策に反映させることができるので、家族にとってだけでなく親自身にとってもメリットがあること。例えば、認知症になった後で法定後見制度を利用する場合、法定後見人など第三者による監督をうけることになるため、制度の運用において親の希望が反映されないかもしれない。一方、認知症になる前に任意後見制度を利用する場合、任意後見人の選定や委任内容に親の希望を反映させることができる
2.親の財産状況の把握
つぎに、親の預貯金と利用している銀行口座について把握しましょう。以下のような内容を含む一覧表を作成できるとよいでしょう。
20XX年XX月XX日現在
| 種類 | 金融機関 | 支店 | 口座番号 | 金額 | ||
| 預貯金 | 普通預金 | ●●銀行 | ●●支店 | XXXXXX | XXXXX円 | |
| 預貯金 | 定期預金 | △△銀行 | △△支店 | XXXXXX | XXXXX円 |
このリストには預貯金のみが記載されていますが、ここに不動産や預貯金以外の金融商品(株式、債券、投資信託など)を追加して財産目録を作成することができれば、その後、相続対策を行うときにも有用なものになるはずです。
ここでも、いきなり親にむかって預貯金の情報を教えてくれ、と切り出しては警戒心をもたれてしまい話がこじれますので、親との信頼関係をつくってからこの作業を行ってください。
また、これは親との信頼関係次第となりますが、預金通帳、キャッシュカード、銀行届出印の保管場所と暗証番号についても親から聞くことができれば理想的です。
なお、これは筆者の個人的な体験になるのですが、親が通帳に記帳するために銀行まで行くのが面倒くさい、というのでインターネットバンキング利用のための手続きをしてあげたのですが、その過程で銀行口座についての情報を暗証番号なども含めて把握することができました。
3.とりあえず金融機関の代理サービスの利用
親が認知症になった場合に備えた対策として、いきなり成年後見制度を利用するのは、専門知識が必要なこと、制度を利用するためのコスト負担、制度利用によるデメリットなどの理由により普通の人にとってはかなりハードルが高いです。
そこで、主に大手銀行がサービス提供している代理サービスの申し込みをしてはいかがでしょうか。代理サービスを利用するには事前に銀行に申し込んで手続きをしなければなりませんが、費用をかけることなく認知症により親の預金口座が凍結されるリスクに備えることができます。
ここでネックになるのが、代理サービスを提供しているのが三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行などの大手銀行に限られていることです。親の預貯金リストにこれらの大手銀行の預金口座がない場合には、これらの銀行口座を新たに開設したうえで代理サービスを申し込むことになります。なお、親がこれまで利用してきた銀行を引き続き利用したいというのであれば、認知症等の病気になった場合に備えるためのお金を代理サービスを利用するために開設した銀行の預金口座に入金してもらうという方法も考えられます。いままで利用したことがない大手銀行の口座を開設することは、高齢の親にとってはハードルが高いというのは容易に想像がつくと思いますが、成年後見制度を利用することの大変さと認知症になった場合の預金口座凍結リスクのことを考えると、この方法をとることが現実的な選択肢にならざるを得ないのではないかと思います。
とはいえ、代理サービスの申し込みは親本人が手続きしなければならないため、親が「やりたくない」、といってしまえばこの方法をとることはできません。その場合には、最低限のリスク対策として、キャッシュカードの保管場所と暗証番号について教えてもらい、できればインターネットバンキングを利用できるようにするのがよいと思います。
4.成年後見制度、財産管理契約、民事信託の検討
金融機関の代理サービスの申し込みをすれば、すくなくとも親が認知症になった場合の預金凍結のリスクには対応したことになります。といっても、親が認知症になった場合にむけて対策が必要なのは預貯金のことだけではありません。たとえば、親が認知症になって施設に入ることになった場合、空き家になった家の処分はできなくなります。このあたりは、親の財産の状況など個別の事情により必要な対策は異なります。そこで、親と家族の意向、資産の状況などを考慮して、専門家に相談しつつ、成年後見制度やそれ以外の代替手段(財産管理契約や民事信託など)の利用を検討しましょう。
まとめ
親が認知症になった場合、家族であっても親の預金口座からお金を下ろすことができなくなります。親が認知症になった場合には、設入居費、医療費、生活費など多額の出費があるかもしれませんが、これらの費用を家族が負担するのは大変なので、親が認知症になる前に対策を準備する必要があります。金融機関は成年後見制度の利用をすすめますが、手続きの複雑さ、費用負担、成年後見制度のデメリットのことを考えると普通の人が成年後見制度を利用するのはハードルが高いでしょう。そこで、大手銀行が提供する代理サービスを利用することで親の預金口座が利用できなくなるリスクに対応することをオススメします。ただし、どのような対策を準備するにせよ、親との信頼関係がなければ準備をすすめることはできませんので、認知症になった場合の備えについて、親と十分なコミュニケーションをすることが必要になります。 そして大事なことは、親が認知症になってしまった後では対応策の選択肢がなくなってしまうので、早めに親とのコミュニケーションを開始してリスク対策に着手することです。
以上
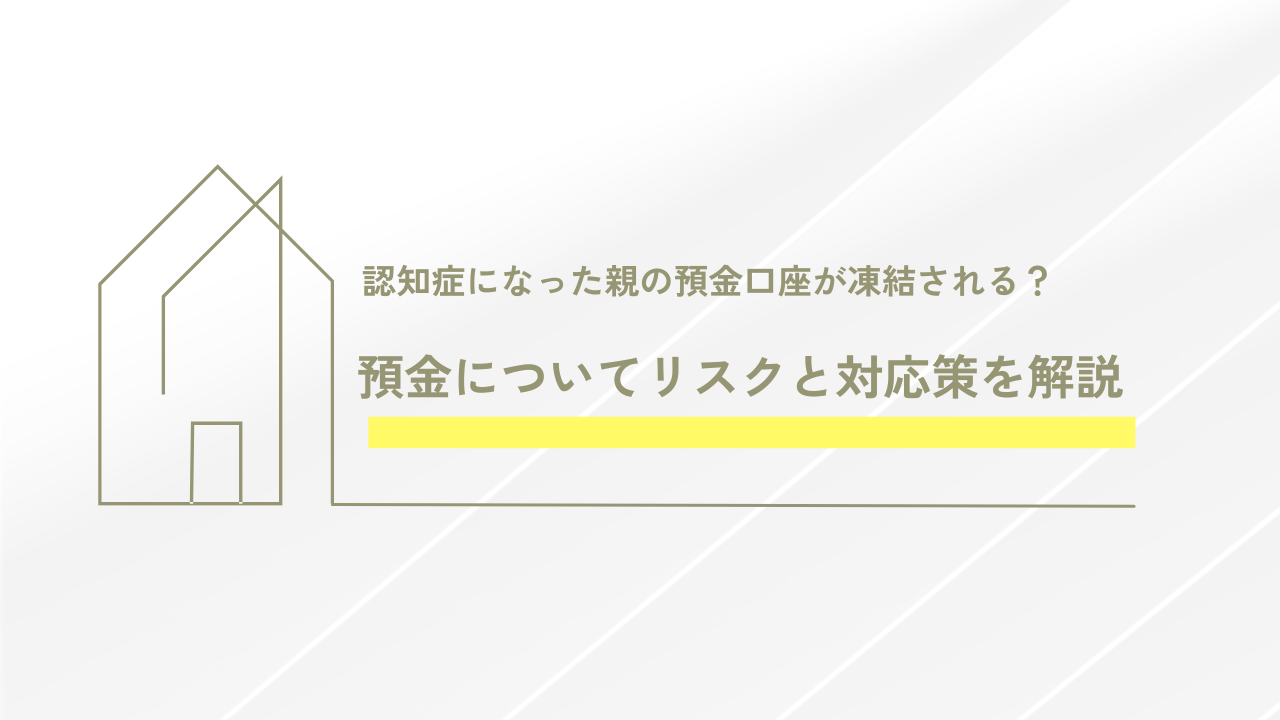

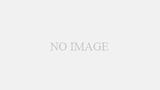
コメント